
「なぜ、同じような失敗を繰り返してしまうのだろう?」
「優秀な人材が揃っているはずなのに、なぜかパフォーマンスが上がらない」
「新しい挑戦が失敗に終わり、チームの士気が下がっている」
といった問題は、多くのマネージャーにとって共通の悩みです。
しかし、その答えは意外なところにあります。
それは、「失敗」との向き合い方です。
私たちは、失敗をネガティブなもの、隠すべきものだと捉えがちです。
しかし、失敗から学び、それを次に活かすことこそが、個人、そして組織の成長を加速させる最大のカギとなります。
そこで、この記事では、ベストセラー書籍「失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織」の内容をもとに、失敗を恐れず、むしろ積極的に活用して成長し続ける組織文化をどう築くべきか、その具体的なヒントを紹介します。
失敗を隠す人の心理:認知的不協和
私たちの進化と成功は、「失敗とどう向き合うか」によって決まります。
しかし、多くの人が失敗を恐れ、隠そうとします。
なぜでしょうか?
まず、誰しも自分の失敗を認めるのは難しいものです。
人は、自分の失敗には言い訳をするくせに、他人の失敗にはすぐに厳しく非難します。
これは、自分自身の自尊心を守るための防御反応です。
失敗を認めることは、自分の無能さを認めることにつながるため、無意識のうちに都合よく記憶を書き換えたり、事実を否定したりしてしまうのです。
この心理的なメカニズムを、社会心理学では「認知的不協和」と呼びます。
これは、自分の信念と行動が矛盾している状態、またはその矛盾によって生じる不快感を指します。
たとえば、「私は有能な人間だ」という信念と「私は大きなミスを犯した」という事実が矛盾すると、人はその不快感を解消するために、自分の行動を正当化しようとします。
ここで多くの人が選択するのは、「自分の信念が間違っていたと認める」ことではなく、「事実の解釈を変える」ことです。
たとえば、「あの失敗は、環境が悪かったからだ」「自分は悪くない、システムが不十分だったんだ」といったように、外部に原因を求めることで、自己正当化を図ります。
「犯人探し」が学習を妨げる:航空業界に学ぶ、失敗から学ぶ組織文化
失敗から学べない組織に共通するのは、「犯人探し」の文化です。
何か問題が起こると、人はその経緯や原因よりも、「誰が悪いのか」を追及しようとします。
しかし、この非難の心理は、組織の学習能力を大きく妨げます。
非難を恐れた従業員は、ミスの報告を避け、問題を隠蔽しようとします。
その結果、失敗から学ぶ機会が失われ、同じミスが繰り返されてしまうのです。
これは、失敗への処罰を強化しても、ミスの報告が減るだけで、根本的な解決にはならないことを意味します。
これに対し、徹底的に失敗から学ぶことで驚異的な安全性を築き上げてきたのが航空業界です。
航空機の事故率は「240万回に1回」と言われるほど極めて低い数値です。
これは、過去のあらゆる事故の失敗を徹底的に分析し、そこから得られた教訓を共有し、システムや手順に反映する努力を絶やさないからです。
彼らは、個人のミスを非難するのではなく、まず何が起こったのか、その事実を丁寧に調査します。
書籍「失敗の科学」では、上下関係がチームワークを崩壊させ、小さなミスが大きな事故につながる例が数多く紹介されています。
上司への配慮から、部下が遠慮してミスを指摘できなかったり、権威者に対し控えめな表現を使ったりすることが、重大な見落としにつながることがあります。
このような問題を解決するために、航空業界では「チェックリスト」を徹底的に活用します。
これは、経験や職位に関係なく、誰もが同じ手順で確認を行うことで、上下関係をフラットにし、ヒューマンエラーを防ぐ役割を果たします。
多くのヒューマンエラーは、個人の能力不足ではなく、設計が不十分なシステムによって引き起こされるという事実を、組織のシステムそのものを見直すことで克服しているのです。
シンプル化の罠から抜け出す:小さな失敗を高速で繰り返す「リーン・スタートアップ」の思想
多くの経営者は、「完璧な計画を立てれば、失敗は防げる」と考えがちです。
しかし、これは「単純化の罠」であり、完璧主義の罠に陥る原因となります。
私たちは、複雑な世界を理解するために、物事をシンプルに解釈しようとする傾向があります。
ただ、この「ヒューリスティックバイアス」や「確証バイアス」は、自分の見つけたい情報だけを探し、それ以外の可能性を無視してしまうことにつながります。
その結果、「机上でひたすら考え抜けば、最適解が得られる」という誤解を生み、実行に移すまでの時間が長くなり、せっかくのチャンスを逃してしまうのです。
書籍「失敗の科学」では、「考えるな、間違えろ」という大胆なメッセージが提示されます。
これは、完璧な計画に固執するよりも、まず小さく始めて、失敗を高速で繰り返すことの重要性を説いています。
これは、シリコンバレーで生まれた「リーン・スタートアップ」の思想と共通します。
「なぜ、一人もユーザーがいないうちからすべての質問に答えようとするんだ?」という問いかけは、完璧な製品を最初から作ろうとするのではなく、必要最小限の機能を持つ製品を素早く市場に出し、顧客からのフィードバックを得ながら改善を繰り返すことの重要性を示しています。
この「量が質を凌駕する」という考え方は、小さな失敗を数多く経験することで、最終的に質の高い成果を生み出すということを意味します。
一発逆転を狙うのではなく、百発逆転を目指し、小さな改善を積み重ねていくことこそ、持続的な成長には不可欠なのです。
「成長型マインドセット」を組織に根付かせる:失敗を恐れない文化の作り方
失敗を恐れずに挑戦し、そこから学ぶ組織になるためには、組織全体に「成長型マインドセット」を浸透させることが不可欠です。
これは、心理学者キャロル・S・ドゥエックが提唱した概念で、人間の能力や知性に対する考え方の違いを示しています。
書籍「失敗の科学」では、
- 固定型マインドセット(Fixed Mindset)
- 成長型マインドセット(Growth Mindset)
という2つのマインドセットの違いが組織に与える影響について、詳細に解説されています。
「固定型マインドセット」とは、知性や才能は生まれつきのもので、ほとんど変わらないと考えます。
結果、失敗は自分の能力の限界を露呈するものと捉え、挑戦を避けるようになります。
一方、「成長型マインドセット」は、知性や才能は、努力によって伸ばせるものだと考えます。
結果、失敗は学びの機会であり、成長のためのステップと捉え、積極的に挑戦します。
固定型マインドセット企業の特徴
- ミスや非難を恐れており、社内でミスが報告されないことが多い
- 他者を出し抜く行為や、作業の手抜きが頻繁に行われる
- 新しい挑戦やリスクを避ける傾向が強い
成長型マインドセット企業の特徴
- 誠実で協力的な組織文化が浸透しており、ミスに対する反応が健全
- リスクを冒すことを奨励し、失敗しても非難されない
- 失敗は学習の機会であり、将来的な付加価値を生むものだと捉えている
- 革新的に考えることが推奨され、創造力が歓迎される
このような組織文化を築くためには、経営者やマネージャー自身がまず成長型マインドセットを持つことが重要です。
「責任を課すこと」と「非難すること」はまったく別物であることを理解し、部下がミスを報告しやすい環境を整える必要があります。
具体的には、ミスが発生した際に、個人を責めるのではなく、「何が起こったのか」を冷静に分析する姿勢を示すことが大切です。
「なぜそのミスが起きたのか?」「どうすれば再発を防げるか?」といった、未来志向の議論を促すことで、チームは失敗から建設的に学ぶことができるようになります。
まとめ
書籍「失敗の科学」は、「失敗=悪いもの」という固定観念を根底から覆してくれます。
失敗から目を背け、隠蔽することは、組織の成長を停滞させ、やがては競争力を失うことにつながります。
失敗は避けるべきものではなく、むしろ積極的に活用すべき貴重な情報源であるということです。
【失敗から学ぶ組織になるための5つのポイント】
- 失敗は恥ずべきことではなく、成長の機会だと捉える
- 失敗に対し、非難よりも、まず事実確認を徹底する(犯人探しの文化をなくす)
- 小さな失敗を高速で繰り返す(完璧な計画に固執せず、行動から学ぶ姿勢を貫く)
- 部下からの率直な意見やミスの報告を歓迎(感謝)する
- 成長型マインドセットを浸透させる(チームの挑戦を後押しする)
特に、組織の経営者やマネージャーは、自らが失敗を恐れず、謙虚に学び続ける姿勢を見せることが求められます。
自尊心や過去の成功体験が、学びを妨げる最大の障壁となり得ます。
過去は事後的に編集される「自己正当化の罠」に陥らないよう、常に客観的に自らの行動を振り返ることが重要です。
書籍「失敗の科学」では、真の無知とは「学習の拒絶」と定義しています。
あなたの組織がこれからも進化し続けるために、失敗から学び続ける「学習する組織」づくりを始めてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【あわせて読みたい】
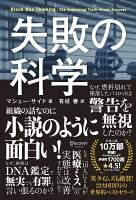


コメント