
「もっと能力があれば」
「自分には能力がないから」
仕事でこんな風に考え、悩んでいませんか?
もしあなたが今、仕事で壁にぶつかったり、自分の能力に自信を失いかけていたりするなら、それはもしかすると「能力」という見えない呪いに縛られているからかもしれません。
そこで、この記事では、書籍「能力の生きづらさをほぐす」の内容をもとに、
- 「能力」という曖昧な概念の正体
- なぜ私たちが能力の幻に振り回されてしまうのか
- 能力の呪縛からどうすれば解放されるのか
について、分かりやすく紹介していきます。
なぜ「能力」は私たちを苦しめるのか?能力の正体とは?
私たちは「能力」という言葉を当たり前のように使っていますが、その定義を明確に説明できる人は多くありません。
にもかかわらず、私たちは常に「能力」という見えない物差しで自分や他人を評価し、比較してしまいます。
定義不明の「能力」がもたらす生きづらさ
書籍では、能力を「幻のように実態のないもの」と表現しています。
というのも、
- ある職場では「優秀」と評価された人が、別の職場では「使えない」と言われる
- 「実力主義」と言われる社会で、努力が報われず、無力感に苛まれる
というような経験は、能力が個人に備わった普遍的なものではなく、きわめて曖昧で不安定なものであることを示しています。
もしあなたの能力が本当にあなただけのものなら、環境が変わっただけで評価が乱高下するなんて、おかしな話ですよね。
これは「仕事には、能力以外の見えない力が働いている」証拠であり、個人の努力だけではどうにもならない現実があることを意味します。
実力主義がもたらす危うさとは、この「見えない力」を無視し、すべてを個人の責任に帰結させてしまう点にあります。
「誰と、何を、どのようにやるか」環境次第で七変化する能力
能力は、個人の所有物のように語られがちですが、実際には「本人が置かれている環境次第で見え方が七変化する」ものです。
たとえば、ソニーで優秀だった人が、必ずしもパナソニックでも優秀であるとは限りません。
これは、その人が持つ能力が劣っているわけではなく、それぞれの会社の文化、チームの人間関係、仕事の進め方といった「環境」との相性が異なるからです。
書籍では、このことを「不幸なミスマッチの可能性」と表現しています。
もしあなたが今、仕事でうまくいっていないと感じているなら、それはあなたの能力が足りないのではなく、単に環境とのミスマッチが起きているだけかもしれません。
能力を個人の責任だけにしてしまうことは、こうした「不幸なミスマッチ」に苦しむ人々をさらに追い詰めてしまう危険性をはらんでいます。
能力主義(メリトクラシー)という社会の仕組み
「努力すれば報われる」
「能力次第で収入が決まる」
私たちは、このような「能力主義(メリトクラシー)」という考え方の中で生きています。
でも、この社会のあり方こそが、私たちを能力の呪縛に縛り付ける根本原因の一つであると、書籍は指摘します。
能力主義社会では、学歴や職歴は個人の努力と能力の結果だと考えられています。
しかし、書籍は「能力は親ガチャ」という衝撃的な事実を突きつけます。
- 生まれ育った環境(親の経済力、教育方針など)が、子どもの学力や能力に強い影響を与えることは、すでに多くの研究で明らかになっている
- 学校教育は、「機会の平等」を装うことで、生まれによる格差を「見えにくく」している
これにより、うまくいかない人は「能力や努力が足りない」と自己責任にされてしまいます。
あたかも、個人の力だけで人生の成功を掴み取れるかのように見せかけることで、社会の構造的な問題から目をそらさせてしまうのです。
しかし、本書が伝える「実力も運のうち」という言葉は、この不公平な社会構造を端的に表しています。
なぜ、「適性検査」や「能力診断」は流行するのか?
仕事の悩みを解決しようと、適性検査や能力診断を受けたことがある人も多いのではないでしょうか?
なぜ、これらのサービスはこんなにも私たちの心を掴むのでしょうか。
人材開発業界が生んだヒット商品「コンピテンシー」
人材開発業界は、企業の「優秀な人材がほしい」というニーズに応える形で、様々な能力の商品化を進めてきました。その代表的なものが「コンピテンシー」です。
書籍では、コンピテンシーを次のように定義しています。
「仕事ができる人は、できる行動をしているからです」
これは、「仕事で高い成果を出している人(ハイパフォーマー)の行動様式を分析し、それを真似すれば誰でも成果を出せるようになる」という考え方です。
コンピテンシーは、一見すると「誰でもできるようになる」という希望を与えてくれる魅力的な考え方です。
しかし、これが新たな問題を引き起こします。
能力の「表層」「中層」「深層」
コンピテンシーは、表面的な「行動」に焦点を当てたものです。
しかし、次のとおり、人間にはもっと深い部分があります。
| 表層(見える) | 知識・経験・スキル | 行動するためのツールであり、習得が容易 |
| 中層(見え隠れ) | マインドセット(意識、意欲、心構え、価値観など) | 容易に変容可能だが、長続きしづらい |
| 深層(見えない) | 性格特性・動機(感情の素) | 若年期に固まり安定するため、変容はかなり難しい |
このように、コンピテンシーが対象とする「知識・経験・スキル」は、氷山の一角に過ぎません。
コンピテンシーに基づき、表面的な行動だけを真似しようとしても、その人の奥底にある「マインドセット」や「性格特性・動機」と合致していなければ、うまく機能しないのは当然です。
「コンピテンシーを軸に採用しても、ぜんぜん活躍できないケースが続出」したのは、この「中層」や「深層」を無視した結果なのです。
性格診断の落とし穴と「違い」を認める大切さ
近年、より個人の深い部分を理解しようと、「性格診断」や「タイプ診断」が流行しています。
書籍では、こうした性格診断の役割を「性格を把握することは、課題解決の最初の一歩」だと認める一方で、その利用法を誤ると、新たな「呪い」を生み出すと警鐘を鳴らしています。
「あなたは〇〇タイプだから、〇〇が苦手だ」といったラベルを貼ることで、私たちはその診断結果に縛られ、自らの可能性を狭めてしまう危険性があります。
大切なのは、「診断結果に書かれている通りに生きる」ことではありません。
この診断を使い、自分と他者の「違い」を踏まえたうえで、「誰と誰を業務で組み合わせるか」「どう仕事を割り振ろうか」と関係性を考えることだと、書籍は指摘しています。
あなたの悩みの本質は「能力」ではないかもしれない
これまで見てきたように、「能力」とは非常に曖昧で、環境や社会の仕組みによって大きく見え方が変わるものです。
にもかかわらず、私たちは「能力」という基準で自分を責め、悩みを深めてしまいます。
能力は「個人」ではなく「組織」が持つべきもの
「企業での活躍に必要な能力」は、時代や企業によってコロコロと変わります。
にもかかわらず、企業は「活躍できる人材を輩出せよ」と大学に求め、個人に「活躍できる能力を身につけろ」と要請します。
しかし、書籍は「能力は、個人に求めるべきものというより、組織が全体の機能として持っておくべきもの」だと主張します。
たとえば、リーダーシップは、個々の社員がそれぞれ持つべき能力ではなく、チーム全体として発揮されるべき機能です。
ある人が苦手な部分を、別の人が得意な部分で補うことで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
「人材開発」ではなく「組織開発」という考え方が重要視されているのも、このためです。
個人の能力を開発するだけでなく、チーム全体の関係性や環境を整えることで、個々の力が最大限に発揮されるようになるのです。
葛藤やモヤモヤは「生きている証」
私たちは、仕事で悩んだり、うまくいかなかったりすると、「自分には能力がない」と結論づけ、早くその苦しみから解放されたいと願います。
しかし、書籍は「葛藤は生きるうえで、必要不可欠なもの」だと語ります。
「今している努力は報われるのか?」
「このやり方で本当にいいのか?」
こうした葛藤やモヤモヤは、未来を不確かだと感じ、より良い道を探している証拠です。
「信頼の土台は、相手を知ろうとして、相手の話をとにかく聞くこと」というように、仕事の悩みも、安易な診断や結論で片付けるのではなく、「ちょっと待てよ?」と立ち止まり、その悩みの奥にある本当の原因に耳を傾けることが大切です。
「ネガティブ・ケイパビリティ(どうにも答えが出せない事態に耐える力)」を大切にし、揺らぎや葛藤を正々堂々とした「生」の一部として受け入れることで、私たちは能力の呪いから解放され、自分らしく働くことができるようになるのです。
まとめ:能力の呪いを解き放ち、自分らしく働くために
あなたが今感じている「能力の生きづらさ」は、あなた個人の責任ではありません。
それは、曖昧な「能力」という概念と、それを基準に個人を評価する社会の仕組みがもたらすものです。
そのため、
- ある評価基準に則った能力という正しさ
- ある職場における『仕事ができる』という正しさ
なんていう、目くらましに惑わされないようにしましょう。
また、仕事でうまくいかない時、私たちはついつい「自分には能力がない」と自己肯定感を下げてしまいがちです。
でも、環境を変えれば、能力の見え方も変わる。
今の職場で評価されなくても、それはあなたの価値が低いわけではありません。
あなたの個性は、誰かと比べるものではありません。
自分と他者との「違い」を理解し、より良い関係性を築くための要素です。
自分を責めることをやめ、前向きに仕事に取り組んでいきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【あわせて読みたい】
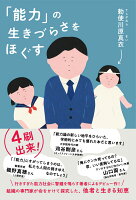


コメント